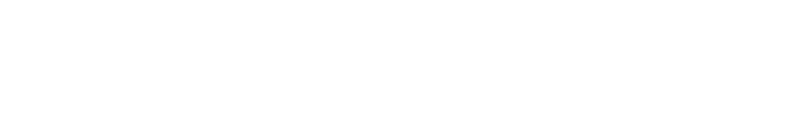十字街電停そばの交差点角に立つ、キノコ型の小さな塔。
これは、かつて市電のポイント(進行方向を切り替える装置)や電車用信号を遠隔操作するために使われた「操車塔」です。
現存する路面電車の操車塔としては国内最古とされ、高さ5.4m、制御室直径1.9mというコンパクトな姿で当時の交通管制を今に伝えます。
操車塔が生まれた背景には、車の往来増加とともに交差点内での人力切り替えが非効率になったことがありました。
1938(昭和13)年に宝来町交差点のポイントが電動化されたのを機に、このキノコ型の操車塔が各所に整備。
かつては十字街・宝来町・函館駅前・松風町・五稜郭公園前・ガス会社前など、市内で6基が稼働し、始発から終電まで職員が中に入り、スイッチ操作でポイントや信号を切り替えていました。
現在残る十字街の操車塔は1939(昭和14)年9月の建設。
現役時代は交差点の向かい側(元北洋銀行十字街支店前)にあり、制御室から行き先を確認して操作していました。
やがて架線機器の改良(トロリーコンダクター等)により自動化が進み、他の操車塔は順次撤去。
十字街の塔も1995(平成7)年6月に役目を終えましたが、同年9月に現在の「アクロス十字街」前へ移設され、形態保存されています。
交差点の景観に溶け込む小さな塔は、函館の市電が育んだ安全運行と街の賑わいの歴史そのもの。
十字街を訪れたら、路面電車とあわせて“キノコ型の交通管制室”にも目を留めてみてください。
昔日のオペレーションが、いまも街角に息づいています。